
監修者プロフィール
本田 茂樹(ほんだ・しげき)
ミネルヴァベリタス株式会社 顧問、公益社団法人全国老人保健施設協会 管理運営委員会 安全推進部会部会員
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社。その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。医療・介護分野を中心に、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、信州大学特任教授として教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
※本記事のうち「BCP研修・訓練にあたり基礎的な知識習得も重要」の章までを監修いただいています。
介護施設の日頃の備え ― 基礎固めおすすめサービス

みえる・まなぶ キラリア感染予防
介護職員・スタッフ様向けの感染予防に特化したオンライン教育プログラム(e-トレーニング)。
現場課題に合わせた最適な教育コンテンツをご提供。
受講前後に実施する自己点検シートによって意識や行動の変化が可視化でき、 知識の定着も図れます。
介護施設におけるBCPとは?
緊急時でもサービスの提供を止めないためには、平時から計画書に基づいて対応を練習しておくことが欠かせません。そこで重要となるのがBCPの作成です。
そもそもBCPとは
BCP(Business Continuity Plan/業務継続計画)とは、災害や感染症といった突発的な緊急事態が発生した際に、業務を継続または早期に再開するための計画のことです。介護施設では利用者の安全確保とケアの継続が最優先されるため、BCPは「緊急時における生命線」といえます。計画書には、大規模自然災害の発生だけではなく、感染症の流行に対しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針や体制、手順に関する内容を盛り込むことが求められます。
BCPの策定は2024年に義務化
BCPの策定、および研修・訓練は、令和3年度介護報酬改定によりすべての介護サービス事業所に義務づけられました。2024年4月1日に制度が開始され、2025年3月末までの経過措置期間を経て、現在は完全に義務化されています。これは、近年の大規模自然災害や新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行を受けた、介護現場の危機対応力を高めるために定められた国の方針によるものです。
介護施設のBCP策定状況
MS&ADインターリスク総研株式会社が実施した調査によると、感染症BCPの策定を完了している施設は82.7%、自然災害BCPは84.7%となっており、いずれも8割以上の施設で策定が進んでいる状況です。しかし進捗が見られる一方で、策定が完了していない施設も存在します。
出典:MS&ADインターリスク総研株式会社「業務継続計画(BCP)の適正な運用に関する調査研究事業報告書 令和7年3月」
未策定時のリスク
BCPを策定していない場合、業務継続への影響が生じる恐れがあります。また業務継続計画未策定減算の対象となり、介護報酬が減額されるリスクもあります。
未策定の場合は、単に策定するだけでなく、業務継続のために実現可能な運用を想定することが大切です。
BCPは感染症・自然災害対策の2種類が必要
介護施設におけるBCPは「感染症」と「自然災害」の2種類の対策を策定することが義務付けられています。これは、介護現場が直面する緊急事態がこの2つに大別されるためです。しかし感染症と自然災害では対応が異なるため、1つの計画で両方に対応するのは現実的ではありません。そのため、二種類のBCPを用意し、状況に応じた具体的な対応を考えておく必要があるのです。
BCPの作成例
介護施設のBCPと一口に言っても、サービス形態によって想定すべき対象や対応内容が異なります。たとえば、入所系ではスタッフや利用者の動線を把握し、安全な避難経路やゾーニングを計画します。一方、訪問系や通所系では、施設内だけではなく送迎中や利用者宅での対応も想定し、施設外のスタッフ・利用者の安全確保と情報連携に配慮する必要があります。このように、サービス形態ごとに具体的なリスクを洗い出し、柔軟にBCPを設計することが重要です。

引用:厚生労働省「厚生労働省 令和5年度 介護BCP策定支援セミナー|BCP作成(入所系)|ひな形(例示入り)を活用したBCP(業務継続計画)の作り方を解説」
厚生労働省が提供する作成例
厚生労働省では、サービス形態ごとにBCPの作成例を公開していますので、自施設に合った例を参考にできます。
感染症対策編
感染症対策は、入所系・通所系・訪問系のサービスごとに、感染リスクの程度や動線、ゾーニング、スタッフの配置などが大きく異なります。作成にあたっての基本的なガイドラインは共通ですが、作成例は施設の形態ごとに公開されています。
| 作成のガイドライン | 作成例 | |
|---|---|---|
| 入所系 | 介護施設・事業所における 感染症発生時の業務継続ガイドライン |
業務継続計画(BCP)感染症編 (介護サービス類型:入所系) |
| 通所系 | 業務継続計画(BCP)感染症編 (介護サービス類型:通所系) |
|
| 訪問系 | 業務継続計画(BCP)感染症編 (介護サービス類型:訪問系) |
参考:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修 」
自然災害編
避難ルートの確保や安否確認、電源・飲料水の備蓄など、基本的な備え・考え方は介護サービス全体に共通します。そこで、作成例はすべてのサービス事業所で活用できる「共通部分用」と、個別の施設特性に応じた「サービス固有用」の2種類があります。
| 作成のガイドライン | 作成例 | ||
|---|---|---|---|
| 共通部分 | サービス固有になる部分 | ||
| 入所系 | 介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン |
業務継続計画(BCP) 自然災害編(介護サービス類型:共通) |
ー |
| 通所系 | 通所サービス固有(P.1) | ||
| 訪問系 | 訪問サービス固有(P.2) | ||
| 居宅介護支援系 | 居宅介護支援サービス固有(P.3) | ||
参考:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
BCPで定めるべき「優先業務」とは
緊急時には通常業務をすべて継続するのは困難なため、特に重要な業務を「優先業務」として位置づける必要があります。
介護施設の優先業務の例:入浴支援、食事の提供、服薬管理など(命や健康に直結する業務)
一方で、緊急時には一時的に中止する業務や、縮小する業務も整理しておくことが重要です。限られた人員や資源で効率よく対応するために、業務の優先順位を定めておきましょう。
BCP研修・訓練とは
策定したBCPを実践に活かすには、スタッフへの理解浸透と実践が不可欠です。そのため、介護施設ではBCP研修・訓練の定期的な実施が義務づけられています。
BCP研修・訓練は法令で定められた義務
BCP研修・訓練は、法令で定められた義務です。令和3年度の介護報酬改定により、BCPの策定に加え、入所系では年2回以上、通所系および訪問系では年1回以上の研修・訓練が必要とされました。また、研修・訓練の実施日時や内容を記録し、管理することも求められています。
BCP研修・訓練の目的と内容
スタッフが緊急時に迷わず動ける体制づくりが、研修と訓練の最大の目的です。研修では、感染症や自然災害への対応知識に加え、BCPの基本やスタッフの役割分担、情報共有方法などを習得します。訓練では、実際の災害・感染症を想定したシミュレーションを通じて、スタッフが業務継続計画に基づいた対応力を身に付けることを目指します。
介護施設におけるBCP研修の進め方
BCP研修では、単に計画を共有するだけでなく、スタッフ一人ひとりが自分の役割を理解し、行動に移せることを目指します。実効性の高い研修を行うための基本ステップを確認しましょう。
①研修の目的と対象者を整理する
まずは、研修を行う目的と対象者を明確にすることが必要です。たとえば「緊急時の初動対応を習得させたい」「平時との対策の違いを伝えたい」といった目的を設定し、それに応じて勤務歴や職種を踏まえて対象を具体的に絞ります。
②①の目的・対象者別に研修内容を設定する
研修の目的と対象者が定まったら、それに合わせた内容を組み立てます。
<対象者と目的に応じた研修内容の例>
| 対象者 | 目的 | 研修内容 |
|---|---|---|
| 新人スタッフ | BCPの全体像と緊急時の自身の役割を理解し、 緊急時の対応力を身に付ける |
・BCPの基礎知識(感染症/自然災害) ・緊急時の行動原則や報告手順 |
| 全スタッフ共通 | BCPの運用を「現場レベル」に落とし込み、 誰がいつ何をすべきかを全員が認識する |
・緊急時対応マニュアルの確認 ・優先業務と対応体制の確認 ・備蓄品・情報伝達手順の理解 |
| リーダー層・ 管理職 | 有事の際のリーダーとしての判断力・指揮能力を強化し、 施設内外の連携ハブとして機能する体制を整える |
・指揮命令系統と判断基準の再確認 ・施設間・地域・行政との連携ルートの整理 |
③研修後は理解度を確認
小テストやアンケートを活用し、内容の定着度を可視化します。その結果を基に、作成担当者は再教育や補足説明の必要性を判断し、研修の質を高めるサイクルを構築しましょう。
介護施設におけるBCP訓練の進め方
BCP訓練は、研修で学んだ知識を実際の行動に落とし込むための重要な取り組みです。緊急時に迷わず対応できるよう、目的や対象者に応じた訓練を効果的に設計しましょう。
①訓練の目的と対象者を整理する
訓練の第一歩は、実施の目的と対象者を明確にすることです。
<目的と対象者の例>
| 目的 | 対象者 |
|---|---|
| 研修で得た知識を実践的なスキルとして定着させる | 新人スタッフ、中途採用者、緊急出勤のスタッフ |
| 緊急時の混乱やパニックを防ぎ、初動対応を迅速に行う | 現場対応を担う介護職、看護職、責任者 |
| スタッフ同士の連携強化や判断力の向上を図る | 全スタッフ |
②①の目的・対象者別に訓練の内容と実施方法を設定する
訓練の実施方法は事業所の判断に委ねられています。目的や対象者、伝えたい内容に応じて最適な訓練手法を選定することが重要です。
<訓練の内容と実施方法の例>
| 内容 | 実施方法 |
|---|---|
| 地震後に施設が孤立した場合の行動 | 机上訓練 |
| 夜勤中に火災警報が鳴った際の避難誘導 | 実地訓練 |
| 新型コロナウイルス発生時の対応 | 感染症対策訓練 |
| 感染症対策訓練 | 通信訓練 |
| 福祉避難所受け入れ訓練など | 連携訓練 |
自然災害と感染症の訓練は同時に行ってもよい
自然災害訓練と感染症訓練は、同時に実施することも可能です。同時に実施することで準備や受講の効率化につながります。また、災害発生時には、衛生環境の悪化や集団生活によって感染症のリスクも高まるため、両者を組み合わせた複合的な訓練は有効です。たとえば「避難誘導中に感染が疑われる体調不良者が出た場合を想定した訓練」という想定で訓練することで、実践的な対応力が養われます。その場合も、記録は必ず残しておきましょう。
BCP研修・訓練に活用できる動画・資料
BCPの研修や訓練を効果的に進めるためには、専門知識や実践的な手順を把握しておくことが重要です。
厚生労働省では、介護施設向けにBCPの作成・運用に関する解説動画や資料を無料で公開しており、研修や訓練の設計に加え、教材としても役立てることができます。
参考:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
BCP研修・訓練にあたり基礎的な知識習得も重要
BCP研修や訓練の実施方法について説明してきましたが、特に感染症対策については、平時から励行すること、スタッフの基礎知識習得を支援することが大切です。これによって、感染が広がるリスクを減らすことができます。とはいえ、すべてのスタッフに基礎知識を身に付けてもらうのは難しいと感じている施設も少なくありません。
こうした課題を解消する方法として注目されているのが、外部の研修支援サービスの活用です。特にオンライン研修ツールは、準備側の負担を軽減でき、スタッフも空き時間を使って受講できるため、双方が効率よく研修を進めるのに役立ちます。
部分的にでも外部サービスを取り入れることも検討するとよいでしょう。
平時からの感染症対策に備える「みえる・まなぶ キラリア感染予防 e-トレーニング」
「みえる・まなぶ キラリア感染予防 e-トレーニング」介護施設のBCPのうち、感染症のまん延防止に役立つ標準予防策などをオンラインで学習できるコンテンツです。教材を新たに作成する手間を削減しながら、スタッフの方の知識を確認する目的でご活用いただけます。
みえる・まなぶ キラリア感染予防 e-トレーニングは動画やクイズで構成されており、医療専門職以外のスタッフの方でも理解しやすく、スキマ時間を活用した受講が可能です。施設全体の基礎知識を底上げすることで、施設内の感染症拡大に対応できる組織づくりを目指せます。
くわしくは商品紹介ページをご覧いただき、オンライン研修導入の一歩としてご検討ください。

サービス資料ダウンロード

みえる・まなぶ キラリア感染予防
介護職員・スタッフ様向けの感染予防に特化したオンライン教育プログラム(e-トレーニング)。
現場課題に合わせた最適な教育コンテンツをご提供。
受講前後に実施する自己点検シートによって意識や行動の変化が可視化でき、 知識の定着も図れます。

.png)
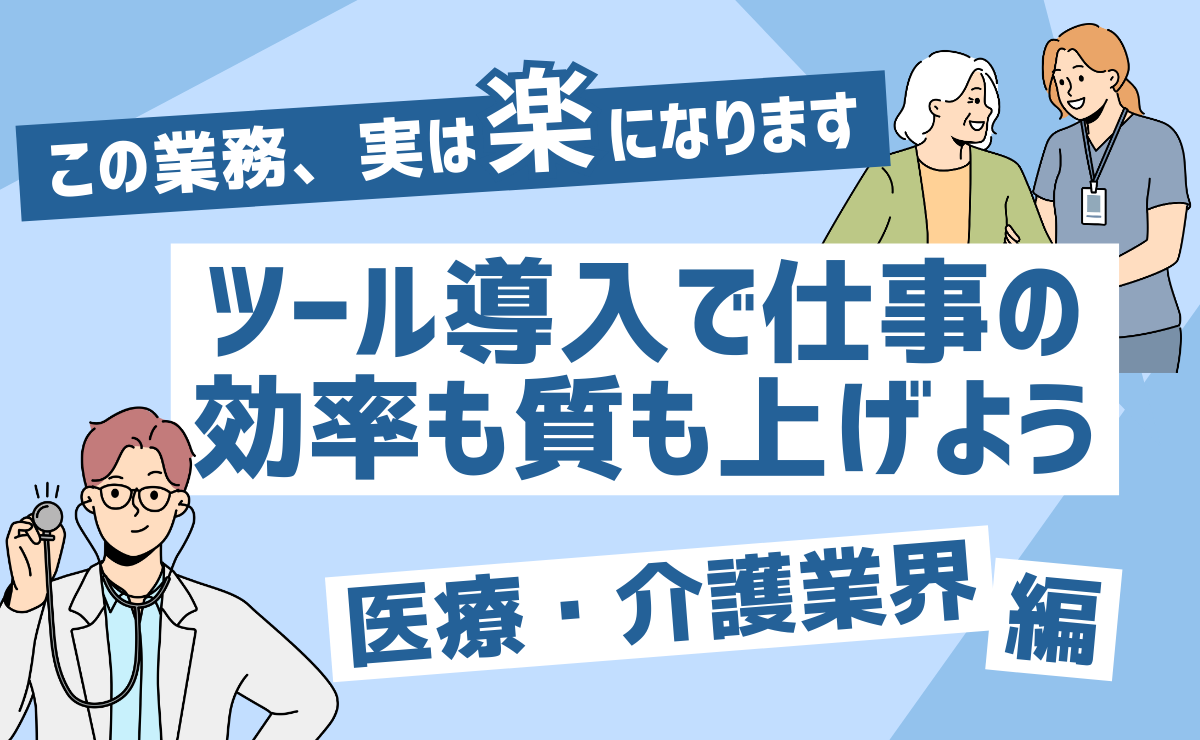
.png)
