今年の年末調整改正点を詳しく知りたい方はこちらの資料もおすすめ!
▶定額減税の計算方法と2025年適用の内容も解説!2024年年末調整に関わる税制改正まとめ資料
近年では、定額減税の実施といったさまざまな変更点によって、年末調整の手続きが複雑になっています。そこで、注目されているのが年末調整の電子化です。本記事では、年末調整を電子化するメリット・デメリットや導入前の準備について解説します。また、年末調整の電子化ツールの選び方についても解説するため、電子化を検討している人は参考にしてください。
年末調整の電子化とは
年末調整の電子化とは、これまで紙をベースにして行われてきた年末調整手続きをデジタル化することです。これによって、電子データでの処理が可能になります。
従来までは紙での記入やチェック、添付書類の内容確認などが必須でした。電子データ処理に移行することで、手続きがスムーズになり効率化できます。
特に2024年度は定額減税の事務手続きが必要で、昨年の年末調整手続きとは異なります。2024年の年末調整では、年末の時点で定額減税の対象者がどれくらいかを算出し、減税額に基づいた年間の所得税額を算出しなければなりません。そのため、従業員が多い企業では、紙での手続きを進めていると大幅な時間が必要となるでしょう。
このような改正後の変更にもすぐ対応できるのが、年末調整の電子化です。年末調整の電子化により、 申告内容の不備への訂正や手続きがスムーズになり、事務処理の軽減が期待できます。
年末調整の電子化ツール導入のデメリット
年末調整の電子化ツール導入にはメリットもありますが、デメリットになる点も存在します。年末調整の電子化ツールを導入する際は、従業員への周知や教育、電子化のルールなどが必要となるでしょう。そのため、電子化ツールを導入して運用するまでに、時間とリソースが必要となる点がデメリットです。
また、これまでの紙での手続きに慣れている場合、電子化の導入により混乱を招く可能性も考えられるでしょう。特にデジタル機器や操作に不慣れな場合は、支援体制を整えるといった新たな業務が増える可能性があります。
年末調整の電子化に必要な準備
年末調整の電子化をスムーズに進めるためには、以下のような準備が必要です。
・マニュアルを作成する
・年末調整の電子化ツールを準備する
ここからは、それぞれの準備について詳しく解説します。
従業員に周知する
先述した通り、電子化ツールを導入する際には、従業員への周知や教育が必要となります。そのため、年末調整の電子化をスムーズに進めるには、従業員への周知を早めに行うことが大切です。具体的には、申告データの取得方法や電子化ツールのダウンロード方法などを周知しましょう。
電子化ツールに対して苦手意識がある方に向けて勉強会の実施が必要となるケースもあるでしょう。事前に十分な情報を提供し、導入前に把握できる時間が必要です。
マニュアルを作成する
年末調整の電子化を円滑にするには、電子化ツールのマニュアルを作成することも必要です。マニュアルの存在により、具体的な手続きの方法だけでなく、注意すべき点が把握できます。
これらの点をできるだけわかりやすく記載することで、従業員が手続きを進めやすくなるため、マニュアルの存在は欠かせません。
年末調整の電子化ツールを準備する
できるだけ早めの段階で、年末調整の電子化ツールを準備することが大切です。クラウドを使っている年末調整ツールなら、多くの従業員がどこからでも手続きしやすくなるため、スムーズな年末調整が期待できるでしょう。
年末調整電子化のモデルスケジュール
年末調整を今後電子化へ移行したい、もしくは移行を検討している場合、以下のようなモデルスケジュールを参考に検討してみてください。
| 時期 | 実施すべきこと |
|---|---|
| 4月~6月 | 年末調整の電子化実施について検討し、必要性に応じて給与システムの改修 もしくは新しいサービスの検討などを実施します。 |
| 7月~9月 | サービス導入後は従業員への周知を行い、マイナンバーカードの取得依頼や 年末調整の実施手順の説明などを行います。 |
| 10月 | 年末調整ソフトの取得、マイナポータルとの連携を設定します。 |
| 11月 | 各従業員は控除証明書等のデータを取得して控除申請書データの作成をして提出します。 |
| 12月 | 企業が年税額計算と精算処理を行います。 |
| 1月~2月 | 法定調書の作成や提出を行います。 |
年末調整の電子化に役立つツールの選び方
ここでは、年末調整の電子化に役立つツールの選び方について解説します。
業種や規模に合った機能か
年末調整の電子化ツールを選ぶ場合、どのツールでも良いというわけではありません。自社の規模業種に合った機能があるものを選ぶ必要があります。
特に従業員数の多い大企業は、高機能なツールによって多くのメリットが得られます。一方、中小企業の場合は、使わない機能がありすぎると使いづらくなる可能性があります。そのため、自社の業種や規模に適したツールを選ぶ必要があります。
例えば、運輸業や建設業の場合、特殊な手当を設けているケースが多いため、特有の控除や手当に対応できるかどうかを確認することがポイントです。ほかにも、紙と電子データの両方を使いたいなら、併用できるかどうかも確認しておきましょう。併用できるツールの場合は、扶養控除申告書を従業員に原本で提出してもらうことが可能です。
既存システムと連携性があるか
すでに企業で取り入れているシステムがある場合、連携性の有無に関しても調べなければなりません。既存システムとの連携性がない場合、データが二重に登録されたり、移行作業を行わなければならなかったりするため、業務効率の低下が起こります。
使用している人事管理システムや給与計算ソフトがある場合は、連携可能かどうか確認しておくと良いでしょう。
簡単に操作できるか
年末調整の電子化ツールを選ぶ際には、従業員がストレスなく使いやすいものか確認しておきましょう。
ツールを選ぶ際は、できるだけ直感的に操作ができるものを選択するのが望ましいです。より詳しい対応ツールを比較したいなら、以下の無料ダウンロード資料をぜひご活用ください。
まとめ:年末調整の電子化は今から準備しましょう
2024年度は定額減税の導入により、これまでの年末調整と変更した点が多くあります。また、2025年度以降も年末調整に関する変更点が複数あると予想できます。制度の変更に柔軟に対応できるクラウド型ツールを活用することで、負担軽減が期待できます。この機会に早めの電子化を検討するのがおすすめです。








.png)
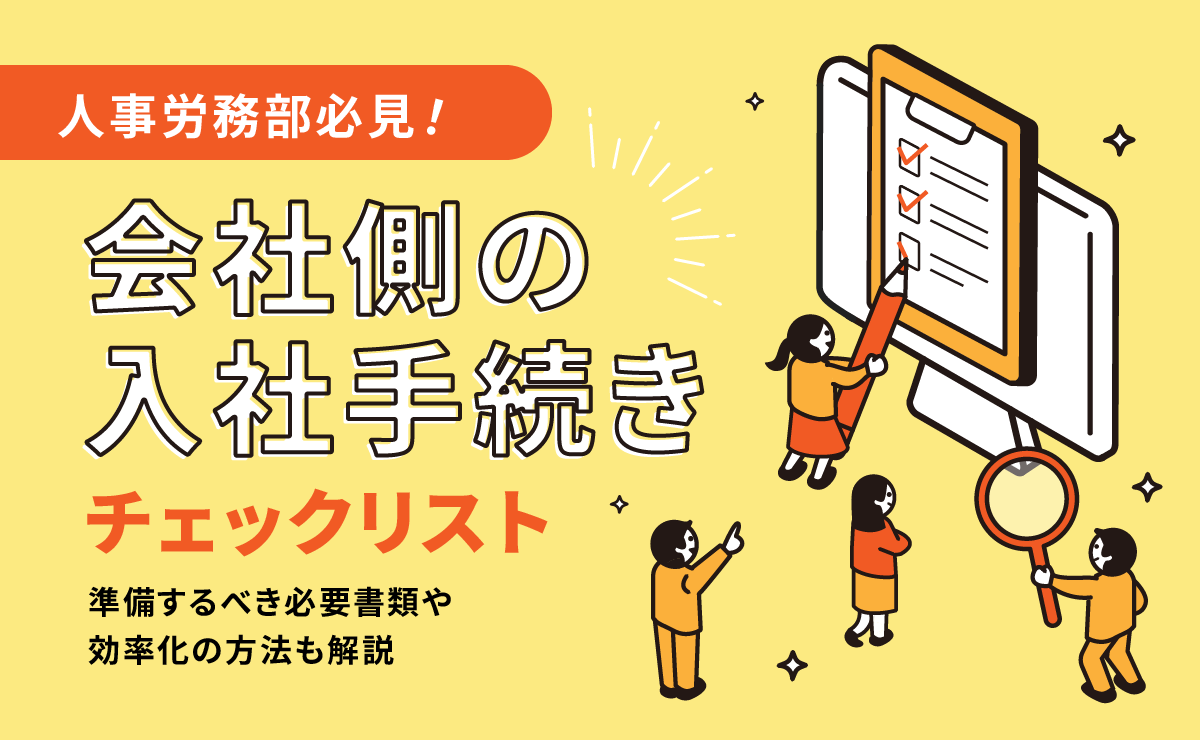
%20(1).png)