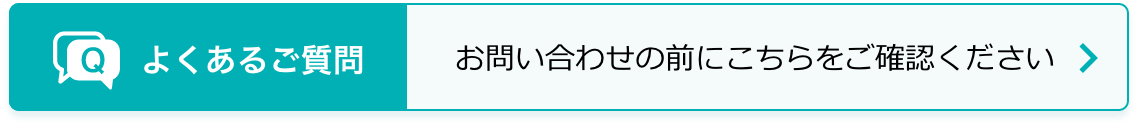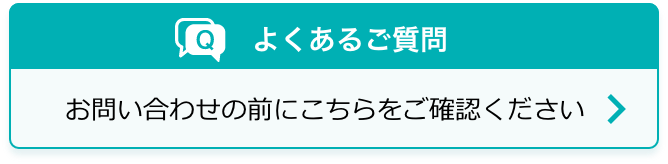ビズらくからのお知らせ
アスクル株式会社運営
「ビズらく」終了のご案内
平素よりアスクル株式会社が運営しております「ビズらく」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、ご愛顧いただいておりました当サイトの運営を終了させていただく事になりました。
様々な企業の皆様にご愛顧いただき、誠にありがとうございました。
【重要】ご契約者の皆さまに
お知らせがございます。
※別ウィンドウでPDFファイルがダウンロードされます